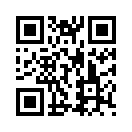2016年02月07日
廃駅とお寺と資料館~函館鉄道乗り歩きと「カシオペア」の旅5~
次の目的地へ向かうために木古内駅へ戻りたいのですが、現在9時40分。次の木古内行きは10時59分。これに乗ると、木古内に11時31分。これでは乗り換えに間に合わないので、いったん反対方向の五稜郭駅まで行きます。

すぐに木古内駅に泊まる特急列車「スーパー白鳥20号」に乗りました。これだと木古内着は11時00分。都合のよい時間です。

気軽に反対方向に行って、特急列車で戻るなんて芸当は特急にただで乗れるフリー切符だからできるのであって、普通なら料金考えるとできない気もします。
木古内駅からは江差病院行きのバスに乗ります。このバス路線に乗るのは2回目。前回は奥尻ムーンライトマラソンの旅の帰りに乗って以来です。そしてこのバスは2014年5月に廃止になったJR江差線の代替バスでした。これに乗ります。前回は沿線市町村のゆるキャラを描いたラッピングバスでしたが、今回は普通のバスでした。

バスからはまだ線路の残っている旧江差線(右の線路)が見えました。

降りたのは鶴岡禅燈寺でした。

まずは渡島鶴岡駅跡へ。待合室の入り口は板が打ち付けられていました。

ちなみに現役時代はこんな感じ

今でも踏切以外の部分には線路が残っていました。

踏切が使われていないという看板は物悲しいものがあります。

渡島鶴岡駅で有名だったものがありました。
この地のお寺、禅燈寺の敷地内を江差線が横切り、踏切があるという場所でした。

ここは今でも残っていました。

「踏切注意」の看板も残っており、この写真だけ見れば、今でも列車が横切りそうですね。
ここ渡島鶴岡は明治以降に山形県の鶴岡市の人々が入植したことから名付けられたそうです。ここにはある程度の人が住んでいたようで、2010年までは鶴岡小学校があったそうですが、閉校になり今では木古内町には小学校が1つしかないそうです。その校舎はまだ新しいので、それを使用した木古内町の郷土資料館「いかりん館」が2015年3月、つい先月に開館したとの情報があったので、今回わざわざやってきたのでした。

今風の小学校の外観ですね。中にはこの館の由来、咸臨丸のものと推定される「いかり」が展示されていました。

ちょうど資料館の人が案内してくれたので聞いてみると、幕末、江戸幕府の使節団とともに太平洋を渡った咸臨丸が、明治に入り輸送船として北海道開拓の人々を運んでいる最中に朝通った泉沢駅付近のサラキ岬で座礁し、沈没したのだそうです。そのサラキ岬付近から発見された「いかり」とのことで、何分明治初期の混沌とした時代の話なので詳しい状況等がわからず、断定はできないものの、おそらく咸臨丸のものであろうということでした。まだ調査中だそうです。
他には木古内町で発掘された土器や、少し前の生活用品が展示されていました。この史料館、学校をそのまま使用していて、フリースペースなんかは本当に学校です。

まだ整理されていないようですが、江差線関係の資料もありました。


木古内駅への帰りのバスがないので、歩いて帰ろうかと思っていたのですが、資料館の人の好意で木古内駅まで送っていただけました。本当に助かりました。
木古内駅からは、またフリーパスを生かして、特急で函館に向かいます。

6へ続く
Posted by さがるまーた at 12:00│Comments(0)
│2015,4 函館鉄道乗り歩きと「カシオペア」の旅
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。